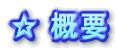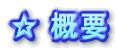

 4~6人で行われることもあるが,ゲームバランスから考えるとベストは5人。以下,5人でのプレイを想定して説明する。
4~6人で行われることもあるが,ゲームバランスから考えるとベストは5人。以下,5人でのプレイを想定して説明する。
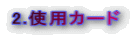
 52枚+ジョーカー1枚=計53枚を使用する。
52枚+ジョーカー1枚=計53枚を使用する。

 各マーク(スペード,ハート,ダイヤ,クラブ)の10.J.Q.K.A,計20枚を「絵札」とする。
各マーク(スペード,ハート,ダイヤ,クラブ)の10.J.Q.K.A,計20枚を「絵札」とする。
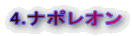
 親のことを「ナポレオン」といい,ナポレオンが指定したパートナーを「副官」,その他3名を「連合軍」という。
親のことを「ナポレオン」といい,ナポレオンが指定したパートナーを「副官」,その他3名を「連合軍」という。

 それぞれに10枚ずつ配り,余った3枚は裏を向けて場の中央に置く。
それぞれに10枚ずつ配り,余った3枚は裏を向けて場の中央に置く。

 ナポレオン,副官を決める(後述)と,ゲームは以下の流れで進行する。
ナポレオン,副官を決める(後述)と,ゲームは以下の流れで進行する。
①
ナポレオンが最初のカード(「台札」という)を出し,時計回り逆順方向の者から順に同じマークのカードを1枚ずつ場に出していく。同じマークのカードを持っていない場合に限り異なるマークを出して構わない(後述する「副官カード」のみ例外の扱いとする)。
② 5枚揃ったところでカードの強さによりその巡の勝者を決定する。
③
その場に出された5枚のうち,絵札は勝者が獲得して自分の前に表を向けて置き,絵札以外は場の中央に裏を向けて流していく。
④
この一巡の勝負を「トリック」といい,計10巡のトリックを繰り返して20枚の絵札を取り合っていく。
⑤ 二巡目以降は前の巡の勝者が台札を出す。
⑥
最初の1巡目のトリックでは,「切り札」(後述)を出してはならない。また,「セイムツー」(後述)は無効となる。

 本ゲームはナポレオン軍2名(ナポレオン+副官)と連合軍3名による団体戦である。
本ゲームはナポレオン軍2名(ナポレオン+副官)と連合軍3名による団体戦である。
 ゲームに先立ちナポレオンは自軍が何枚の絵札を獲得できるか宣言をしておく。
ゲームに先立ちナポレオンは自軍が何枚の絵札を獲得できるか宣言をしておく。
 10回のトリックを終えて各自の手札がなくなったとき,絵札の獲得枚数により以下のように勝敗を決する。
10回のトリックを終えて各自の手札がなくなったとき,絵札の獲得枚数により以下のように勝敗を決する。
① ナポレオン軍が宣言枚数以上の絵札を獲得していた場合はナポレオン軍の勝ち。
② ナポレオン軍が宣言枚数以上の絵札を獲得出来なかった場合は連合軍の勝ち。
③
どちらの軍においても,20枚すべての絵札を取ってしまった場合は負け。ただし,ナポレオン軍において「20枚獲得」の宣言がなされていた場合はその限りではない。

 ゲーム終了後,各人に以下のポイントが与えられる。
ゲーム終了後,各人に以下のポイントが与えられる。
①
ナポレオン軍勝利の場合:ナポレオン+2,副官+1,連合軍それぞれ-1
②
連合軍勝利の場合:連合軍それぞれ+1,ナポレオン-2,副官-1


 カードの強さは後述する「切り札」「役」という二つの例外を除き,原則として以下の順で判断していく。
カードの強さは後述する「切り札」「役」という二つの例外を除き,原則として以下の順で判断していく。
①
スペードのAは「オールマイティ」(略して「マイティ」)と呼ばれ,「台札」や「切り札」(後述)に関係なく最強のカードである。ただし,例外として負けるケースが2通りある(後述)ので注意が必要である。
②
台札と同じマークのカードがなく,異なるマークのカードを出した場合は,数字(2.3.4・・・8.9.10.J.Q.K.A)に関係なく負けとなる。
③ 台札と同じマークのカードを出した場合は,その数字によって以下の順に強い。
A > K >
Q > J > 10 > 9 > ・ ・ ・ 4 > 3 > 2

 ナポレオンは4つのマークのうち1種を他の3種よりも強いマークとして指定することができる。このマークを「切り札」,他の3種のマークを「平札」という。
ナポレオンは4つのマークのうち1種を他の3種よりも強いマークとして指定することができる。このマークを「切り札」,他の3種のマークを「平札」という。
 「切り札はなし」というも選択できる。この状態を「ノートランプ」(ノントラ)という。この場合,以下の「切り札」に関するルールは一切ないものとしてゲームを進めることになる。
「切り札はなし」というも選択できる。この状態を「ノートランプ」(ノントラ)という。この場合,以下の「切り札」に関するルールは一切ないものとしてゲームを進めることになる。
 「切り札と同色別種のJ」のことを「裏ジャック」といい,このカードは「切り札」として扱う。例えば切り札がハートならばダイヤのJ,切り札がクラブならばスペードのJが「裏ジャック」である。「裏ジャック」は台札のマークに対しても「ディファレント7」(後述)に対しても,元のマークではなく切り札のマークとして扱う。また,「裏ジャック」と区別して元々の切り札のJのことを「表ジャック」という。
「切り札と同色別種のJ」のことを「裏ジャック」といい,このカードは「切り札」として扱う。例えば切り札がハートならばダイヤのJ,切り札がクラブならばスペードのJが「裏ジャック」である。「裏ジャック」は台札のマークに対しても「ディファレント7」(後述)に対しても,元のマークではなく切り札のマークとして扱う。また,「裏ジャック」と区別して元々の切り札のJのことを「表ジャック」という。
 台札と同じマークのカードがなくて異なるマークのカードを出した場合,「平札」ならば原則通り負けとなるが,「切り札」ならば勝ちとなる。つまりマーク間においては以下の強弱関係が成り立つ。
台札と同じマークのカードがなくて異なるマークのカードを出した場合,「平札」ならば原則通り負けとなるが,「切り札」ならば勝ちとなる。つまりマーク間においては以下の強弱関係が成り立つ。
「切り札」 > 「台札と同じマークの平札」 > 「台札と異なるマークの平札」
 「切り札」同士の間での強さは,その数字によって以下の順で強い。
「切り札」同士の間での強さは,その数字によって以下の順で強い。
J(表ジャック) > J(裏ジャック) > A
> K > Q > 10 > 9 > ・ ・・ > 4 > 3 > 2

 特定の条件においては「役」が発生し,原則とは異なる基準で強さを判定する。
特定の条件においては「役」が発生し,原則とは異なる基準で強さを判定する。
①
「セイム2」(S2)
一巡のトリックがすべて同じマークの平札であった場合,2が出ていれば「セイムツー」という役が発生し,2の勝ちとなる。
②
「ディファレント7」(D7)
一巡のトリックに全4種のマークが揃った場合,7が出ていれば「ディファレントセブン」という役が発生し,7の勝ちとなる。複数の7が出た場合は,スペード>ハート>ダイヤ>クラブの順で強い。すべての強さの判定基準のうち,この「ディファレント7」がもっとも優先度が高く(つまり最強),「オールマイティ」にも勝つ。
③
「切り札請求」
ジョーカーを台札として出した場合,「切り札請求」という役が発生し,他の者は切り札を,切り札がない場合は絵札を,絵札がない場合はもっとも大きな数字のカードを出さねばならない。このとき,ジョーカーは「表ジャック」と「裏ジャック」の間の強さのカードとして扱われる。ジョーカーは台札以外としてはいつでも好きなマークの代わりとして出せるが,その場合は役が発生せず,無条件で負けとなる。このとき,マークはなしという扱いになるので「セイムツー」は成立しない。
④
「よろめき」
「オールマイティ」と同じ巡にハートのQが出た場合,「よろめき」という役が発生し,ハートのQの勝ちとなる。他の役との競合については③より強く,②には負ける。
⑤
「マイティ請求」
スペードの3を台札として出した場合,「マイティ請求」という役が発生し,オールマイティを持っている者は(たとえそれが「副官カード」であったとしても)必ず出さなければならない。ただし,スペードの3の強さは通常と変わらないので,そのトリックの勝敗は通常通り判断される。
 以上をまとめると,それぞれの役が発生したときの優先順位・強さは以下の通りとなる。
以上をまとめると,それぞれの役が発生したときの優先順位・強さは以下の通りとなる。
| D7 |
> |
よろめき |
> |
マイティ |
> |
「切り札」 |
> |
「台札と同じマークの平札」 |
> |
「台札と異なるマークの平札」 |
= |
「台札でないジョーカー」 |
|
・ |
切札同士における強さ |
:表J > 切り札請求 > 裏J > A > K > Q > 10 >
9 > ・ ・ ・ > 4 > 3 >
2 |
| |
|
平札同士における強さ |
:S2 > A > K > Q > J > 10 > 9 > ・ ・
・ 4 > 3 > 2 |
|

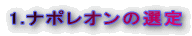
 ナポレオンの選定は以下の手順で行う。
ナポレオンの選定は以下の手順で行う。
①
カードの配布後,各自が自分の手札を評価し,ナポレオンになりたい者は早い者順で「切り札ハートで12枚」というように「どのマークを切り札にして何枚の絵札を取るか」を宣言して立候補する。立候補する意思のない者は「承認」と宣言する。
②
あとから立候補する者は,より上位の宣言,すなわち先に立候補した者以上の枚数を宣言しなければならない。
③
枚数が同数の場合は,切り札がノートランプ(後述)>スペード>ハート>ダイヤ>クラブの順でより上位の宣言とする。
④
自分より上位の宣言がなされた場合は,さらに上位の宣言をして改めて立候補することができる。また,一度「承認」しても途中から改めて立候補しても構わない。
⑤
このようにより上位の宣言を繰り返していくことを「セリ」といい,最終的に最上位の宣言を他の全員が「承認」すると,その宣言者にナポレオンが決定する。
⑥ 宣言枚数は過半数である11枚以上でなくてはならない(10枚以下の宣言はできない)。
⑦
立候補者がいないときは,中央に余った3枚を公開して改めて募る。それでも現れない場合は,オールマイティを所有しているものが強制的にナポレオンとなる(マイティ責任という)。オールマイティが場の中央に出ている場合は,ジョーカーを持っているものが強制的にナポレオンとなる(「ジョーカー責任」という)。ジョーカーも場の中央に出ている場合は,カードを配り直す。

 副官の指定は以下の手順で行う。
副官の指定は以下の手順で行う。
①
ナポレオンは,確定すると同時に好きなカードを「副官カード」として指定する。このとき副官カードを所持していた者が自動的に「副官」となる。
② 副官となった者は,そのことを明らかにする必要はない。
③
次に,ナポレオンは中央に伏せられた余りの3枚を自分の手に加え,13枚の中から好きな10枚を手元に残すことができる。不要となった3枚は裏を向けて中央に置く。不要な札のうち絵札がある場合はそのカードだけ表を向けて中央に置く。
④
このとき,もしも副官カードが加えた3枚の中に入っていた場合は,ナポレオンが副官を兼任することとなる。この状態を「ナポレオンソロ」といい,一人で4人の連合軍に立ち向かうこととなる。
⑤
副官カードは台札のマーク指定に従わなくてよいという特権をもつ。つまり台札で指定されたマークのカードが「副官カード」しかなくても,隠匿して出さないことが許される。

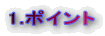
 ゲーム終了後,各人に以下のポイントが与えられる。
ゲーム終了後,各人に以下のポイントが与えられる。
①
ナポレオン軍勝利の場合:ナポレオン+2,副官+1,連合軍それぞれ-1
②
連合軍勝利の場合:連合軍それぞれ+1,ナポレオン-2,副官-1

 ゲーム中は戦略上の嘘は許される。つまり自分が副官であるか連合軍であるかといったことについて偽っても構わない。また,ナポレオンが「副官カードを出してくれ」などと呼びかける等の行為も許される。
ゲーム中は戦略上の嘘は許される。つまり自分が副官であるか連合軍であるかといったことについて偽っても構わない。また,ナポレオンが「副官カードを出してくれ」などと呼びかける等の行為も許される。
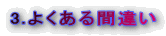
 「副官の選定」で述べたとおり,副官カードは台札のマーク指定に対して特権的に隠匿することはできる(台札と同じマークのカードが副官カードしかなくても出さなくてよい)が,出すときには特権はない(例えば副官カードがオールマイティであったとすると,台札にハートが出されたとき,ハートのカードがあれば必ずそれを出さなければならず,オールマイティを出したくても,出すことはできない)。
「副官の選定」で述べたとおり,副官カードは台札のマーク指定に対して特権的に隠匿することはできる(台札と同じマークのカードが副官カードしかなくても出さなくてよい)が,出すときには特権はない(例えば副官カードがオールマイティであったとすると,台札にハートが出されたとき,ハートのカードがあれば必ずそれを出さなければならず,オールマイティを出したくても,出すことはできない)。

 ナポレオンには数多くのローカルルールが存在し,またルールの解釈も異なるものが多数ある。ここで紹介したルールのうち,ローカルルールと思われるものを断っておく。
ナポレオンには数多くのローカルルールが存在し,またルールの解釈も異なるものが多数ある。ここで紹介したルールのうち,ローカルルールと思われるものを断っておく。
① 「ディファレント7」
採用されているところは少ないようである。ただし,終盤の攻防・駆け引きを大いに盛り上げるのでぜひ採用したい。
②
「切り札請求」
ジョーカーの扱いはかなり多様なようである。オールマイティより上位に位置づけるルールや,ワイルドカードとして使うルールもある。また,同じ「切り札請求」でもジョーカーの強さは様々なルールがあるようで,ここでの「表ジャックより下,裏ジャックより上」という位置づけは少数派のようである。
③
「マイティ請求」
これも採用しているものは少数のようである。また,ジョーカーをオールマイティよりも強い位置づけとしているルールでは「ジョーカー請求」という役を採用しているところもある。
④ その他,用語についても異なった呼称が存在するようである。
⑤
ゲーム中の三味線(嘘)を禁止したり,会話を禁止する厳格なマナーを推奨するところもあるが,三味線も含めて自由に会話した方が断然面白い。
以上,管理人が中学時代に先輩に教わったルールを記した(09.09.06)